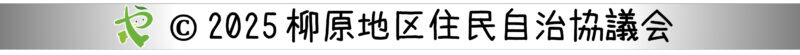二つとも旧郵便局東側の国道沿いにある。大正8年4月道路法が制定され道路整備が進む。8月には内務省令によって各市町村の道路元標の設置位置・表示・材料・規格など定められた。
柳原村の元標もそれに従って、材料は石材の25cm四方の角柱、地上より見える高さ65cmにして上部は面をとり「上水内郡柳原村」と刻む。設置位置は初め「柳原村大字柳原字堀1886-3」とされ道路に面した道端に立てた。
「しろばし」は城橋だという。中俣城を往来するために北八幡川関係の川にかけた橋の標示石(ひょうじいし)だろう。元標も「しろばし」も道路工事のたび移動している。
● 道路元標・しろばし近辺の地図
● 上水内郡柳原村 の歴史
・江戸時代 – 前身の水内郡村山村・布野村・中俣村・小島村は松代藩領であった。
・1870年(明治6年)7月 – 小島村・中俣村・布野村・里村山村 (千曲川を挟んで村山村があったが、長野市側の村山村を「さとむらやまむら」と呼んだ) の4ヶ村組合立の巡回学校 (長野市立柳原小学校の前身)が開校。
・1876年(明治9年)5月30日 – 水内郡布野村・中俣村が合併して柳原村となる。
・1879年(明治12年)1月4日 – 郡区町村編制法の施行により、各村が上水内郡の所属となる。
1889年(明治22年)4月1日 – 町村制の施行により、上水内郡村山村・柳原村・小島村の区域をもって柳原村が発足。
・1954年(昭和29年)4月1日 – 柳原村が長野市に編入。同日柳原村廃止。旧村山村域は大字村山、旧柳原村域は大字柳原、旧小島村域は大字小島となる。
●「しろばし」 の名前の元になっている中俣城とは
築城年代は定かではないが応永年間(1394年〜1428年)に井上氏によって築かれたと云われる。
井上左馬助光頼の弟遠江守が在城し、後に村上氏の支配下となった。弘治年間(1555年〜1558年)には武田氏の所有となってその家臣が在城したが、武田氏が滅亡すると上杉景勝の支配下となり家臣 本田安房守(あわのかみ)が在城した。
中俣城は現在の城山稲荷の付近に築かれていた。城山稲荷神社一帯が本丸で、北東に二の丸、北に三の丸があったと云われる。現在は遺構がなく、城山稲荷神社の所に案内板があるのみである。